Vol.4 語り手 勝本昌宏氏
アルバローザを巡るさまざまなこと
戦後のファッションを見直す機運が盛り上がっている。そんな中以前からアルバローザを知る人々に「アルバローザの現象とはなんだったのか」「日本のファッション史の中のアルバローザとは」等をテーマに、それぞれの立場から見たアルバローザについてお話を伺ってきたが、今回はそのシリーズの第4回目。
アルバローザはどんな人たちの手によって作り出されたのか、生地やプリントや織物の手配に奮闘したワイエムケー・テキスタイルの営業担当・勝本昌宏さんに当時のお話をうかがった。
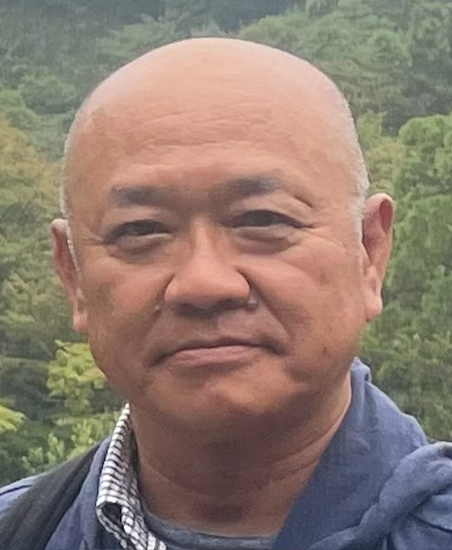
プロフィール
1965年横浜市生まれ。
家業の生地問屋の紹介で、1985年、20歳で服地生地の卸商社・株式会社ワイエムケー・テキスタイルに入社。
アルバローザの営業担当をしていたマテリアルテキスタイル アドバイザー間野弘和氏の下で仕事を学びながらアルバローザの素材開発に参画。生地の手配、プリント工場や織物工場とのパイプ役として密に関わり、当時はアルバローザに席があるのではないか、といわれるほどほぼ毎日通い詰め、デザイナーと共に商品を作り上げた。
現職 株式会社ワイエムケー社長
第4回 時代を牽引したアルバローザは
どのような人の手を介して作られたのか
1990年前半から日本のファッション界で一大旋風を巻き起こし、社会的現象にまでなったアルバローザ。その人気の秘密は、他にはない深い色合いのプリントも大きなポイントの一つだった。デザイナーたちの難しい要求、それを受ける現場の職人たちの間に入り、営業マンとして日々奔走した勝本さん。どのように仕事をすすめ、新しいファッションを世に送り出したのだろうか。アルバローザ製品誕生の臨場感あふれる現場の日々を語っていただいた。
入社後、すぐにアルバローザの担当に
リゾートファッションに向かう現場と出会う
横浜というと今はおしゃれなイメージですが、僕が生まれ育った当時は、家の近所の川の側に染料の工場や長屋が建ち並ぶ、いわゆる下町といった風情が残っていました。その頃の横浜といえばシルクが有名で、戦前からシルク関係の商社が本社を置くくらい繊維業が盛んな場所でした。戦後は職人の技術を生かしたプリントと高品質のシルク素材で海外でも人気を博した「横浜スカーフ」の製造で栄えていました。生地を切り売りする店も多く、僕の家が生地関係の問屋を営んでいたこともあって、父親の縁で1985年、生地卸しの商社であるワイエムケー・テキスタイルに入社しました。
とはいっても、20歳の僕は横浜近辺に土地勘はあるものの、なんとなく繊維業界の端っこをかじっているだけの素人でしたから、とにかく仕事を覚えなければなりません。そのときの教育係だった上司の間野がアルバローザとよく仕事をしていたことから、僕も“生地を納める業者”のドライバー兼雑用係として、すぐに東京・千駄ヶ谷にあるアルバローザの事務所に毎日のように通うことになったのです。
1985年頃のアルバローザは横浜相鉄ジョイナス店がオープンした頃。創業社長の加藤会長と営業4~5人、企画兼デザイナー2人の全社員で7~8人という規模で、ハイビスカスのモチーフはあったものの、まだロゴはありませんでした。でも、裸足にスリッポン、白いGパンという出で立ちの加藤会長が、「リゾートファッションをやりたい!」と熱く話していたことをよく覚えています。ものすごいインパクトでした(笑)。
当時のファッション業界は、原宿のラフォーレが賑わい、DCブランドが盛り上がっていて、オーダーメイド製品が当たり前の時代から、S・M・Lという決まったサイズから選んで買い、服を使い捨てる大量生産に移り変わる時代でした。
その流れの中で小さなファッションメーカーがたくさん生まれ、千駄ヶ谷界隈に集まっていました。ワンルームマンション50~80戸のすべてがファッションメーカーで、「マンションメーカー」という言葉ができたほどです。小さな部屋で起業して、そこで基盤を作って会社を大きくして原宿に巣立っていく、そんな「原宿ドリーム」がありました。
ワイエムケー・テキスタイルは、自社の仕入れ先や関係先等を使って、マンションメーカーの立ち上げからやりたいことの実現までをお手伝いする、という業務を行っていました。ファッション業界はバブル期前の85年から景気が良くて、バブル期の90年頃まで、ファッションメーカーのどこの部屋も夜の11時まで灯りがついているくらい忙しかったのです。その分儲かりましたが、使う時間がないほど忙しく、お金は貯まりましたよ。そんな時代でした。
過酷な職人たちの現場から
価値の高いハンドプリントが作り出された
大量生産時代のファッション業界では、効率の良いマシンプリントが中心になっていましたが、そうした工場に発注すると、注文の単位が1000、2000メートルからになるので、大量に売りさばくことになります。85年当時のアルバローザの規模では難しい面がありました。そこで、上司の間野が、「町工場の職人がハンドプリントする手捺染なら、繊細な色が出せて味わいがあるし、少量から発注できる」と提案したのです。
ただ、ハンドプリントはマシンプリントと違って、ひとつひとつの工程に手がかかるのです。まず色味の調合から全て手作業ですが、こだわりの強いデザイナーが望む色をいきなり出せるわけではないので、発色テストのために色見本を用意しなければなりません。例えば、一つの図案で背景のベースカラーがピンク、ブルー、ブラウン、イエローの4配色あり、モチーフが10色使いの場合、全40色作らなければなりません。色を作るときは、染料をきっちり測り、経験からのちょっとしたさじ加減で色の調整をして、1色刷るごとに版を洗うという工程ですから、色見本を作るだけで何時間もかかるのです。

色のOKが出ると次にはプリントの作業が始まります。これも大仕事です。50メートルひ と巻きの生地を25メートルの捺染台と呼ばれるプリント台2台に貼ります。図案の中の色の数だけ版を作るのですが、図案が大きいと、その版は横幅約2メートルにもなり、二人で刷ることになります。1色ずつ色を入れていくのですが、まず1台の生地にプリント、それも生地を汚さないために図柄ひとつ分ずつを空けながらプリントして行き、次の台にも同じようにプリントしながら帰ってくる。そして染料が乾いたら、空間の部分をプリントして往復。1色ずつ、プリント位置がズレのないように重ねてプリントしていきます。10色使うものであれば1柄刷るために20往復。そうして生地一巻き分24セットができあがります。こうした作業を行うのは規模の小さい町工場が多く空調設備が十分ではないので、夏場であれば工場内は55度という過酷な暑さです。本当に重労働の職人仕事なのです。
でも、その分、出来上がりが違うのです。どうしてかというと、マシンプリントが写真のような出来上がりなら、ハンドプリントは絵画のように手で描いた味わいを表現し、繊細に仕上がるのです。
アルバローザからは、デザイナーだけでなく全国の直営店店長達にも、このような繊細な作業を見てもらいたいとプリント工場見学をお願いされました。それは、職人の苦労や事情を知って、全員で商品価値を共有するための配慮でした。


アルバローザのスタッフにも怒鳴る上司から
取引先との間合いを教わった
アルバローザの代表商品であり、定番商品でもあるのが、レーヨンスムースという素材で作られたハンドプリントのワンピースです。レーヨンスムースは、レーヨン70%ポリエステル30%という混率の、プリントの下地用に編まれたアルバローザオリジナルの生地で、90年に誕生しました。
ポリエステルが入っている分、柔らかな風合いでシワになりにくく、旅行に最適なアイテムとして人気に火がつき大ヒットしました。一般的には2種類の素材が混ざっているものは、使う染料が違ってうまく染まらないので、プリント用の生地としてはあまり使いません。レーヨンスムースの場合も、レーヨンの染料でプリントするとポリエステルの部分が染まらず白く残って色落ちしたように見えていました。

でも、それがかえって良かったのかもしれませんね。黒で染めたものは「スミクロ」と言われ、アルバローザっぽいカラーになりました。
レーヨンスムースのワンピースを始め、アルバローザがハンドプリントをずっと大事にしていたのは、「数は少なくても価値の高い商品を作りたい、大量生産をして在庫を抱えるのではなくいい商品を次々と出していきたい」と考えていたからだと思います。
ただ、ハンドプリントには難しい点もあります。人が一枚一枚刷っているのでどうしてもムラが出てしまう。また、生地によって染まり方が違うから、指示された色が出ないこともあり、その調整で時間がかかってしまうのです。
ですが、現場の事情を知らないアルバローザのスタッフからは「まだですか?」と催促がくる。そんなときは上司の間野が、「カラーコピーじゃないんだから、そんなにすぐできるか!」と工場の立場に立って平気でスタッフに怒鳴っていました。
逆にアルバローザのスタッフからプリントの仕上がりにクレームが入れば、「違うじゃねぇか!」と工場にもすぐに電話して怒鳴った。双方の間で、ときには強面で仕事をしていました。
間野からは、なんでも下手に出て「すみません」と言えばいいわけではない、時には相手に厳しく言わなければいけない、という営業のやり方を教わりました。
一方で、間野は提案型の営業ではなかったから、お客さんと商品について意見が対立することはなかった。僕も発信するタイプではなく、お客さんの難題を「何でもやれます」とかなえていく営業スタイル。だから個性の塊だった加藤会長を始め、こだわりの強いアルバローザのデザイナー達と一緒に仕事ができたのだと思います。

予算にこだわらず、自由な発想で
業界の常識をくつがえす商品を作った
前述したように、加藤会長は「リゾートファッションをやりたい」という熱い思いを持ちつつスタッフに自由に企画を提案させて、面白いと思ったらその人に責任を持ってやらせるという人でした。
だから、僕もお客様のリクエストに応えるために生地や資料を探しによく出張に行きましたよ。ウールなら愛知県の一宮、デニムなら岡山へ、マスクをして古い倉庫に一日中こもって掘り出し物を見つけようと一生懸命でした。
加藤会長も市川社長も、こちらの提案に「いいじゃん!」と言ってくれて、いくらかかるか気にもせず、すぐ企画にゴーサインを出してくれました。他の企業なら、こちらが見積もりを出して、相手が予算内に収まるかなど様々検討して、その後企画が動き出すという流れですが、アルバローザは違います。
そんな感じなので、デザイナーさん達もこだわりをもって、自由な発想でどんどんチャレンジしていました。
96年に発売されたデザイナーの大井さんの企画で、間野が担当したストレッチパンツのこともよく覚えています。パンツの片脚に大きなハイビスカス柄、もう一方の脚に葉の柄がプリントされているこの商品は、生地の段階では不自然な位置に柄が出るため、職人達からは「なんだ、これ?」と不思議がられました。でも型紙を置いたところに柄が入るようになっていて、商品になると無地と柄の左右の格差が格好よく、人気がありました。

ただ、僕はよく「もったいないなあ」とも思っていました。というのも、プリント柄は小さければどのようにカットしても同じような柄が出やすいのですが、不規則な上にハイビスカスの柄が大きいとどうしても生地を捨てる部分が多くなって無駄が多い。業界用語で言うと「取り都合が悪い」のです。
アルバローザでは、この「取り都合が悪い」ことを逆手にとってモノマネ対策をしていました。ハイビスカスや籠の柄を部分的に欠けさせる特徴的なデザインに人気が出てくると、渋谷109の「ミ・ジェーン」には、どこかの生地屋さんやデザイナーさんらしき人が参考にするためなのか、商品をよく買いに来ていました。
そこで、柄の繰り返しをオートプリントできる80センチ程度ではなく、例えば二人でハンドプリントしなければできない1メートル50センチ以上にして、取り都合が悪い贅沢な仕様にしたのです。とても安売りメーカーに真似できるものではなかったですよ。
ただ、1メートル50センチの布を全配色分取っておくと色見本の控えが山のようになってしまって、よく間野が困っていました(笑)。それで無地の部分を捨て、大きな絵刷りの一部分だけを切り取って保管していたのです。
僕が担当したこともあって印象に残っているのが、デザイナーの堤さんが企画した半袖のネルチェックです。ネルは通常冬物の生地。半袖は今まで見たことがなかったので、初めて話を聞いた時はびっくりしました。
当初は小ロットでも請け負ってくれる新潟の工場で、機械を2台だけ稼働して50メートルの生地を4反から始めました。それが最終的には20反まで作ったと思います。

スタートから数ヶ月後に工場見学に行くと、全ての機械でネルチェックを作るようになっていて、その光景には感動しましたね。
今になって思うと、アルバローザは独自性の高い商品を色々作りましたね。それで、自分が担当したものをお店に見に行こうとすると、「カジュアル」や、「ミセスキャリア」といった今までのカテゴリーにあてはまらないものばかりで、どこの売場なのかよくわからなかった。アルバローザは、ファッション業界の既成概念にないスタイルのブランドだなぁと思ったものでした。
こだわりの強いデザイナーが他に無いものを作ろうとするから、仕入先は無理難題を形にしないとならないので大変なんです。
そういうわけで、アルバローザの忘年会は、得意先ではなく仕入れ先を労うために開かれる年末の会でした。行ったこともないような高級店に僕ら仕入れ先を招待してくれたので、一張羅のジャケットを用意して楽しみにしていましたよ。
アルバローザと共に駆け抜けた時代を経て
05年に全店舗が閉じて、一緒に幕を閉じた
在籍していたワイエムケー・テキスタイルは社員10人くらいの小さな会社でしたが、最盛期の2000年前後には十数億くらいの売上げがあって、その約半分を間野と僕が担当するアルバローザの仕事で稼ぎ出していました。うちの会社はアルバローザと共に大きくなっていったのです。僕にとってもアルバローザは仕事を覚えさせてくれたところで、二つの会社に所属しているくらいの気持ちでした。
その後、ガングロブームが起きて、ブランドイメージが一人歩き始めました。そして、マスコミからブランドの本質とは違ったイメージで報道されるようになっても、本来の良さがわかる人にわかればいいのかなと思っていたので、05年に全店舗を閉じると聞いたときは本当に驚きました。うちの会社もそのタイミングで間野が定年になり、会社自体も一緒に、一つの時代の幕を閉じました。
その後、僕はワイエムケー・テキスタイルの歴史を引き継ぐ形で、別会社ですが今の会社ワイエムケーを立ち上げました。20年間ともに過ごしたアルバローザで学んだことを大事にしながら、今もテキスタイル業界で頑張っています。


